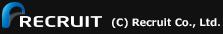王道ではなく、あえて横道に。光石さんの感性にぴったりはまったのはW110型の“ハネベン”でした
「子供のころに50’sブームの洗礼を受けて、10代 はキャロルやクールス、ダウン・タウン・ブギウギ・バンドにのめり込んでいましたね。その影響もあって、古着や昔のアメ車が好きでした。ただ自分のキャラクターを冷静に考えると、トライシェビーって柄でもないなって感じて、同時期の“ちょっとアメリカの匂いがする”ヨーロッパ車に傾倒していったんです」
俳優を目指して福岡から上京。初めて買った足 はベスパ50S。そして20代前半でボルボ122S(アマゾン)を手に入れた。ちょうどこの頃、本企画と同じように有名人の愛車を紹介している雑誌を目にしたそうだ。登場していたのは、多くのファッション誌で活躍していたイラストレーターのクルマ。それがFin Tail、日本では“ハネベン”と呼ばれるM・ベンツW111だった。「ページの中にいたツートーンカラーのハネベン はとにかくきれいでした。しかも後日、青山の骨董通りに止まっているのを偶然見かけたんですよ。『うわ、雑誌に載っていたやつだ』って。この出会いでハネベンが頭の中にインプットされてね。以来、ずっと憧れ続けていたんです。ところがまだ20代前半でお金がなかったので、仕方がなくボロボロのアコードを3台乗り継ぎました」
40代になった頃、再び旧車に対する憧れがふつふつと湧いてきた。もちろんハネベンを考えたけれどタイミングよく出会うことができず、縦目のW114をチョイス。そこにちょっとした“事件” が起こる。友人から「ハネベンが見つかった」という連絡が入ったのだ。「W114を買った直後だったから『残念だけれど 今は無理だよ』と断りました。ところがこのW114 はあまり程度が良くなくてね。2年ほどで我慢できなくなって買い替えを考えた時に、たまたま雑誌でハネベンの記事を見つけたんですよ」
光石さんはバスをとことこと乗り継いで、取材に協力していた店へと向かった。すると目の前にあるクルマこそが、2年前に友人が知らせてくれたW110型のハネベンだったことを知る。「僕が憧れ続けていたのは縦目のW111ですが、 偶然の出会いに運命を感じてしまってね。『W111 はちょっとギトギトしているかな、丸目のほうが可愛げがあるかな』という感情が生まれてきました(笑)。しかもソリッドなグレーはブリキのおもちゃのような雰囲気がある。そんな部分も気に入ってこの63年式W110を買うことにしたんです」まだ駆け出しだったころ、2CVやバンプラなどで撮影現場に来る先輩を眩しく感じ、いつか自分もそんな俳優になることを夢見ていた。1年半ほど前にW110を手に入れ、まずエンジンをオーバーホール。時間もお金もかかったが、日常の足として問題なく使えるレベルに仕上げることができた。撮影現場にW110で出かけることも多い。「憧れのクルマを手に入れたことで、仕事の往復がとても楽しみになりました。特に帰りは時間を気にしなくていいから、好きなソウルミュージックをかけながら街を流してみたりしています。しかもこのクルマはコラム式のMTなので、大好きなクルマを自分がダイレクトに操っているという感覚を存分に味わえるんですよ」
光石さんは旧車をピカピカにして乗るよりも、年式相応のヤレ具合を残しておいたほうがカッコいいと感じている。だから錆びが目立ち始めたバンパーや少し塗装がひび割れてしまったフィン部分は、あえてそのままに。「僕はナルシスティックなものが苦手なんです。そのせいか、スポーツカーもあまり得意ではなくてね。すべてを完璧にキメるのではなく、ウールパンツにスニーカーという、ちょっと着崩した雰囲気を楽しむほうが性に合っているんですよ。そう考えると、王道のW111ではなくW110というのも、僕らしい選択だったのかなと思いますね」

text / TAKAHASHI Mitsuru photos / OGATA Kazumi